むかし語り(十三) ― 2010/10/04 23:05

雨は上がり風もやみ、凪いだ朝の海を船が行く。船底に隠れていた弟と私はすぐに見つかり、祖父の前に引っ張り出された。大人たちの叱責の声をものともせず、私は背筋をしゃんと伸ばし言った、私はたしかにまだ年若いし半人前だが、れっきとした職人である、祖父も私を有望だと褒めてくれたではないか。もう父母の助けがなければ生きられない幼児でもない、自分の面倒は自分でみる、何としても私は祖父と一緒にいきたいのだ、どうしても駄目というならここから落とせ、泳いででもついていく。船の縁に足をかけようとする私を周りの大人は慌てて止めたが、祖父は微動だにせず、一言も言葉を発しない。するとずっと黙っていた弟が口を開いた。我は祖父に命を救われた、その左目と引き換えに我はここに生きている、だから我の命は祖父とともにあるべきなのだ。船の上はしんと静まった。弟は更に言った、これが我のすべき仕事である。
その言い方は祖父にそっくりだった。周りの大人達は固唾をのんで祖父の顔を見つめていた。祖父は低く笑って、わかった、二人とも好きにしろ、ただし皆の足を引っ張らないようにするのだぞといった。船の上は歓声に包まれ、弟と私は大人たちにもみくちゃにされた。雲ひとつない青空の下、眩しく輝く海原の向こうの島。高鳴るばかりの胸の奥に時折よぎる不安の正体を、その時の私はまったく理解していなかった。

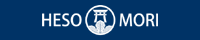

最近のコメント