秋を待ちながら ― 2013/09/02 20:29
9月になりました。とはいえ外はまだまだ夏の暑さ・・・せめて芸術の秋を、ということで改めて越前和紙に縁の深い画家さんたちをご紹介。使われている紙はいずれも時代は違えど、岩野平三郎さんの工場で作られたものです。
まずはこちら、
「明暗」横山大観・下村観山画。1927(昭和2)年、直径445cm。
かつての早稲田大学図書館、現在會津八一記念博物館に所蔵されています。作品管理の都合上、特別な行事の時以外は公開していないとのこと。
使われている特注の和紙は当時世界最大の5.4m四方・重量は紙だけでも12kgあるそうです。
まずはこちら、
「明暗」横山大観・下村観山画。1927(昭和2)年、直径445cm。
かつての早稲田大学図書館、現在會津八一記念博物館に所蔵されています。作品管理の都合上、特別な行事の時以外は公開していないとのこと。
使われている特注の和紙は当時世界最大の5.4m四方・重量は紙だけでも12kgあるそうです。

・・・・・
大階段に近づくにつれ、隠れていた太陽が徐々にその姿を現すのを体感できるはず。漆黒の暗雲の中から日輪が上るその瞬間を描いたこの大作は、大学という場で学ぶことによって、暗闇から明るい世界へと進みうることを示しています。
・・・・・「早稲田ウィークリー」記事より抜粋
大階段に近づくにつれ、隠れていた太陽が徐々にその姿を現すのを体感できるはず。漆黒の暗雲の中から日輪が上るその瞬間を描いたこの大作は、大学という場で学ぶことによって、暗闇から明るい世界へと進みうることを示しています。
・・・・・「早稲田ウィークリー」記事より抜粋
次はこれ、圧巻の
「唐招提寺障壁画」東山魁夷。
何度も日本渡航を試みながら失敗し、盲てもなお諦めずついに念願を果たした唐の僧・鑑真和上。彼がついに自分の目で見ることの叶わなかった日本の風景を描いています。

そして鑑真像を安置している部屋には、彼の故郷・揚州の山。

魁夷はこの絵を描くために、鑑真に捧げる日本の風景を探し歩き、中国も訪れたそうです。
これら芸術作品の凄いのは、ただ「絵」そのものだけではなく、描かれる紙、嵌めこむ襖、設える建具、天井や床のデザインや素材、観る人の動線に至るまで沢山の人の手と思いがすみずみまで行き渡っているところでしょう。名の残る画家や職人と、名も無き無数の人の技と心がひとつになることで初めて出来る「場」、これぞ日本ならではの究極の「芸術」であろうと思います。
このような仕事の端っこにでも身を置けたら・・・と想像するとぞくぞくしますが、何となく関わった人たちの大部分は大して名誉だとも光栄だとも思わず、気負うことなく淡々と自分の仕事をこなし、終わったら普通に自分の生活へと戻っていったのではないかという気もします。そういうところがまたいいですね(と勝手に解釈)。そういう人に私もなりたい。
これら芸術作品の凄いのは、ただ「絵」そのものだけではなく、描かれる紙、嵌めこむ襖、設える建具、天井や床のデザインや素材、観る人の動線に至るまで沢山の人の手と思いがすみずみまで行き渡っているところでしょう。名の残る画家や職人と、名も無き無数の人の技と心がひとつになることで初めて出来る「場」、これぞ日本ならではの究極の「芸術」であろうと思います。
このような仕事の端っこにでも身を置けたら・・・と想像するとぞくぞくしますが、何となく関わった人たちの大部分は大して名誉だとも光栄だとも思わず、気負うことなく淡々と自分の仕事をこなし、終わったら普通に自分の生活へと戻っていったのではないかという気もします。そういうところがまたいいですね(と勝手に解釈)。そういう人に私もなりたい。
引き寄せるもの ― 2013/09/04 17:36
昨日、思いがけない贈り物が。
「和紙文化辞典」 久米康生・著 発行:わがみ堂
「和紙文化辞典」 久米康生・著 発行:わがみ堂

古書店で偶然この本を目に留めたとある方が、私と私の実家のことを思い出して送ってくださった。
わがみ堂、とは東京都文京区にある「和紙のわがみ堂」。装丁はもちろん和紙。著者の久米さんは元毎日新聞記者で、退職後から和紙の研究に専念され、去年まで和紙文化研究会の代表でいらした方。
大体が和紙というのは昔から、特殊技能故に常に時の権力者の庇護を受け、基本的に門外不出とされていた。そのせいで技術的なことのみならず歴史そのものもあまり多くの人に知られることなく、必然的に学問として専門的に研究されることもほとんどなかった。
確かに、和紙関係の本というのは探してみると、意外なほど少ない。私の知っている数少ない本には、必ずやこの久米さんの名前がある。和紙、特に昔ながらの手漉きの和紙は本当にごく一部の方の熱意により消えずにここまで来たのだなあと実感する。
しかしこの辞典、実にタイムリーで驚いた。私は紙漉きの家に生まれ育ったものの、ただそれだけで、紙漉きのことについて何も知らない。川上御前の御名を借りながらこのていたらくではいけない、と近年になって慌てて勉強している最中である。全国の和紙や道具や技、著名な職人の名前、製法の説明、全国の紙郷分布、歴史年表、和紙文化関係の主要文献に至るまで索引つきで掲載されているこの辞典、まさに今の私に必要な本だ。何かこう、逃れられない縁に引き寄せられたような、そんな気がする。
師匠、ありがとうございました。精進いたします。

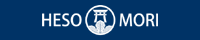

最近のコメント