皆さま、良いお盆休みをお過ごしでしょうか? 私はこの夏休み諸般の事情でどこにも出かけられず蟄居生活をしております。ものを読んだり書いたりするにはうってつけですね♪(泣)
というわけで(どういうわけだ)、ここで「職人」について考えてみます。
※こちらで書いている内容は、様々な資料や本から関連したトピックをまとめたものです。詳しく知りたい方は文末の「参考」欄のサイトや本をご覧ください♪
現代日本において職人とは?
鎌倉期に「職人」とされる人びとのなかには、医師・陰陽師・巫女・博打・万歳法師(芸能)など職能民全体がふくまれていました。自分の技能を使って何らかの仕事をする人、という大きいくくりだったのでしょう。室町期以後は職人といえば上記の定義のとおり主に手工業者をさす言葉となったようですが、まだはっきり業種が分けられていたわけではなく、田畑を持ち農村で生活しながら物を作りさらに運搬・販売までしていた者も多かった。職人の多くは商人をもかねていたということです。
顧客より直接注文を受け生産・販売するというやり方で、商人の仲介販売利益を排除しようとした…ともいわれています。「職人」も「商人」もかなり古くからいたということですね。ものをつくる人というのはある意味わかりやすいですが、商人ってそもそも何をする人だったのでしょう?
「虹が立つ」ところに市場をたてるという慣習
人と人の間で物を交換するというのは「贈り物をして、お返しを貰う」という贈与互酬の行為です。つまりその関係をより強固にする目的ですることであり、商行為とはいえません。では「商品としての交換」はどのようにして行うか。
「モノがモノとして相互に交換されうるためには、特定の条件をそなえた場が必要、その場が市場である。市場においてはじめて、モノとモノとは贈与互酬の関係から切り離されて交易をされる…市場は日常の世界とは関係ないいわば『無縁』の場として古くから設定されてきたのではないか」(勝俣鎮夫)
「虹が立つところに市をたてる」という慣習は、平安時代の貴族の記録にもあり、室町時代にもまだその名残があったそうです。驚くべきことに日本以外の他の民族にも共通した慣習が存在するといいます。つまり市場は
「神の世界と人間の世界…聖なる世界と俗界の境(=虹の立つところ)に設定される」。
何か厨二心をくすぐる(笑)壮大な表現ですが、要するに日常の関係性に関わりなく、商品を以て自由に交渉ができる場ということです。現代の市場原理の原点ともいえますね。
技術を持つ人は神仏の直属民
そもそも金融の始まりは以下の「出挙(すいこ)」と呼ばれる流れだそうです。
初穂を神に捧げる→神聖な蔵に保管→翌年種籾として農民に貸与→収穫期、借りた種籾とともに若干の利息をつけて(利稲)蔵に戻す、の繰り返し
人智を超えた神仏に捧げられたものを人間世界で使用した場合、神仏への礼として利息をつけて返すという形がとられていた。このようにどうやって利を得るかを考え実行するのは、相当の知恵と機転がないとできないでしょうから、神仏の世界に通じる特殊技能のひとつとされたのも納得がいきます。
このころの商工業者は、特定の領主の支配する荘園の範囲をはるかに超えて、市場から市場へと活発に移動していました。職人たちは寺社神仏に奉仕する神人などの身分を得て、領主の支配領域にとどまらない活動の自由を保証されていたのです。金融や交易、ものづくり、芸能等秀でた技を持つ人は神仏に直接仕える者として、一般民と区別されていました。
もっとも神に近いところにいた「職人」たちは同業組織としての座をつくり、権威ある寺社神仏の加護と、土地の権力者に支えられて営業権を保証されていました。が、その排他性と特権が職人同士の対立を生み、さらに顧客と職人の自由な交渉と契約に基づかない在り方は産業の衰退を招くとして否定され、戦国期の終わりには楽市・楽座が行われるようになりました。領主の権力範囲からはみ出し利益を独占していた座や株仲間などは廃止され、絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免など新興の商工業者を支援・育成し経済の活性化を図ったのです。
南北朝時代を境に、従来の神仏に対する意識が変わり、それに伴って金融や交易、手工業に携わる人たちの身の処し方も変わっていったようです。しかし細かい事情は違うにしろ、まさに歴史は繰り返す…と思ってしまうのは私だけでしょうか?
ともあれ本来の意味での「職人」とは、
「ただひたすらものづくりに集中する」だけではなく、
神仏を敬い、
商売の世界と日常とを明確に分け、
権力に阿ることなく対等に渡り合って
したたかに生き抜いてきた存在である
ということらしいです。
参考:
「日本の歴史をよみなおす(全)」網野善彦 ちくま学芸文庫
「神と紙 その郷」


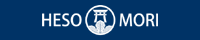

コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。