続いてきた理由 九 ― 2017/08/02 10:20

白山信仰の祖である泰澄大師が開いた大滝神社。しかしいわゆる「白山神社」ではありません。もちろん一世を風靡した信仰ですから影響は色濃く受けていますし、白山信仰にはつきものの十一面観音も鎮座ましましておりますが、地元民にとっては昔も今もあくまで川上御前への信仰が中心です。
「大滝寺」ができた719年は、のちに深く仏教に帰依することになる首(おびと)皇太子(=聖武天皇)が初めて政務についた年でもあります。遣唐使は前回の倍以上の557人。一気にグローバル化が進み、風土記や日本書紀の編纂事業・増え続ける公文書や仏教経典の写経用等々質の良い紙の需要が右肩上がりのこの時代、既に紙すきの里として200余年を数える大滝を福井生まれの泰澄大師が知らないはずはないし見逃すはずもない。白山を開いた直後いち早く「吉兆をみて」向かったところをみると、最初から目をつけていたのでしょう。むしろ山より紙すきの現場視察をし、その確かな技術と生産体制を確認した上で寺の建設を決めたのでは?とさえ思ってしまいます。
紙の産地であることがもっとも重要な理由であったからこそ「白山」を前面に押し出すことはせず、元々の神である紙祖神・川上御前を尊重した……と考えると、「技術」というのは本当に「神」そのものだったのですね。
大滝寺は天台宗平泉寺の末寺として、48坊をもち衆僧600人、神領70町余、氏子48か村という大勢力をもつに至りました。奈良時代から平安にかけ五箇で漉かれた紙は越前国府や大滝寺に納められ、のちに平泉寺が比叡山延暦寺と関係を持つようになると、京都へも送られるようになりました。時の権力者をその高い技術と生産力で魅了した和紙の里とともに最盛期を迎えた大滝寺は、皮肉にもその強大な力ゆえに否応なく戦乱に巻き込まれていきます。
ところであの「越前奉書」、始まりは南北朝の時代といわれています。そんな大変な時代になぜ?
※南北朝時代とは
14世紀前半から後半にかけ、朝廷VS幕府の争いから各地で武士の権力争いに発展した内乱の時代。鎌倉時代後半から皇位継承問題に幕府が干渉し、二つある皇統どっちも正当ってことで交代で皇位につきましょ!(=両統迭立 りょうとうてつりつ)という方式を成立させ余計にこじらせた。陰謀渦巻き裏切り寝返りなんでもあり・遠方に流されたり落ちのびたりした先で武士や権力者を味方につけリベンジ→さらに裏切り寝返り……のループでますます泥沼化、戦乱は全国規模に拡大した。ややこしいことに年号も南北で分かれています。以下北朝・南朝の順で表記:
1336年(建武3・延元元年)北朝方の斯波高経(しば たかつね)が越前守護となる
1337年(建武4・延元2年)南朝方の新田義貞が敦賀・金ヶ崎城に立て籠もり高経(北)と激戦、義貞(南)敗走
1338年(暦応元・延元3年)義貞(南)が勢いを盛り返し越前府中を掌中に収め、高経(北)敗走。しかし藤島城の平泉寺衆徒が高経(北)側に寝返り、義貞戦死。
1341年(暦応4・興国2年)南朝最後の拠点とされた大滝寺が北朝軍に攻められ陥落
1342年(暦応5・興国3年)高経(北)は当時の五箇紙漉きの代表者・道西掃部(どうさい かもん)に
「立派な御教書用の紙を漉いて差し出すように」
と命じた。五箇の漉き屋は戦乱で逃げ散っていた職人を呼び戻し、力を合わせて漉いたという。そうして出来上がった紙が非常にすぐれていたため高経は喜び、これに
「立派な御教書用の紙を漉いて差し出すように」
と命じた。五箇の漉き屋は戦乱で逃げ散っていた職人を呼び戻し、力を合わせて漉いたという。そうして出来上がった紙が非常にすぐれていたため高経は喜び、これに
「奉書」と名をつけた。五箇の漉き屋も喜んで
「出世奉書」
と名づけて生産に励んだという。これが五箇奉書の始まりと伝えられている。
「出世奉書」
と名づけて生産に励んだという。これが五箇奉書の始まりと伝えられている。
--------
最初に越前守護となったのは北朝方。なのに大滝寺は北陸における南朝最後の拠点とされています。(戦場となったのは今の大滝神社ではなく、別の場所の出城なのではないか?ともいわれているが、何しろのちに織田信長の軍勢に焼き討ちされてしまっているためわからない)平泉寺を通じ延暦寺と関係があったことを考えると、元々南朝方だったのかもしれません。
どちらにせよ大滝寺がこのように戦火に巻き込まれ焼け落ちても、翌年には守護の命を受け現在にも繋がる高品質の新製品を生み出した和紙の里の人々は、相当にしたたかで冷徹、かつ有能な商売人でもあったと思います。

参考:神と紙その郷 紙祖神岡太神社・大滝神社 重要文化財指定記念誌
越前市ホームページ/越前市の歴史年表
続いてきた理由 八 ― 2017/06/13 10:30
気がついたら「七」から一年以上過ぎてた…気を取り直してゆるゆる続きます。

さて、紙祖神・川上御前を祀る大瀧神社は来年の1300年大祭を前に、地元でさまざまな準備が同時進行しております。「わし太夫」にボチボチ記事が載っておりますが、大祭は地域にとって大規模メンテナンスの絶好の機会でもあります。年数を経て傷んできた箇所の点検・補修・改修は神社仏閣にとどまらず、一人一人が自分の家やその周辺も整えるため、地域全体が一種独特の緊張感に包まれます。33年ごと・50年ごとという、昔の平均寿命を考えると人ひとり一生に一度あるかないかのお祭りを、時の政権や法律等に依らない地元民のコミュニティレベルで代々繋いでいくシステムが成り立っているというのは驚くべきことです。
以下、御開帳(おかいちょう:33年ごとに行われる仏式の節目の大祭)と御神忌(中開帳 なかがいちょう:50年ごとに行われる神式の大祭→来年はこちら)が行われた年代と回数を示します。
なお1575(天正3年)に織田信長の武将・滝川一益により大滝寺の堂舎は焼亡、これより前の資料は失われたため、記録に残されているのは1585年以降です。
なお1575(天正3年)に織田信長の武将・滝川一益により大滝寺の堂舎は焼亡、これより前の資料は失われたため、記録に残されているのは1585年以降です。
1585(天生13年) 第26回 御開帳
1617(元和3年) 第27回 御開帳
1618(元和4年) 900歳 御神忌
1650(慶安3年) 第28回 御開帳
1667(霊元7年) 950歳 御神忌
1683(天和3年) 第29回 御開帳
1716(正徳6年) 第30回 御開帳
---この年6月、享保と改む
1718(享保3年) 1000歳 御神忌
1748(延享5年) 第31回 御開帳(3/20-4/20)
---この年7月12日、寛延と改む
1768(明和5年) 1050歳 御神忌
1780(安永9年) 第32回 御開帳(3/23-4/23)
1812(文化9年) 第33回 御開帳
1818(文化15年)1100歳 御神忌(3/5-11)
1844(天保15年) 第34回 御開帳(3/23-4/23)
---この年12月2日、弘化と改む
1866(慶応2年) 1150歳 御神忌
1876(明治9年) 第35回 御開帳(4/27-5/1)
1908(明治41年) 第36回 大祭典
1918(大正7年) 1200年大祭(4/14-20)
1940(昭和15年) 第37回 式年大祭(6/11-15)
1968(昭和43年) 1250年大祭(5/2-5)
1973(昭和48年) 第38回 式年大祭(5/3-6)
2009(平成21年) 第39回 式年大祭(5/2-5)
そして来年、
2018年(平成30年) 1300年大祭(5/2-5)
となっています。ちなみに何で来年が1300年かといいますと、大滝神社の始まりが719年とされているからです。(数え年ですね)
719年。前年に白山を開闢した「越の大徳」泰澄大師が戸谷村(旧武生市戸谷町)にて説法をしていたとき、南東の方向に毎朝紫雲がたなびくのを見た。不思議に思いその地を訪ねたところ、清い滝がありその響きが音楽のようであったため里の名を大滝と改めた。さらにその滝の東北東にある山を登ると杉の大木があり、枝が紫雲に覆われていた。峯を巡ると白山が見えたので拝願し、
「この山は霊地であるから権現の御影向(ごようごう)を図(うつ)したまえ」
と一心に祈念すると、白山より金色の大光明が放たれ、5・6歳の児(ちご)が大師の膝の上に来現、たちまちにして白玉と化したのでこれを石唐櫃に納め埋められた。以後、川上御前を含む神々を祀る大滝兒(ちご)権現、大滝寺が開創された。
(この縁起については「泰澄大師御自筆の巻経があったが、信長軍の攻撃により焼失したため元祖大師から伝聞し授受した所を付記」したとする天正13年9月6日付の記録が残っている)
小さな里の祭りが、これだけの長い年月、社会状況が大幅に変わっても途切れることなく、そればかりか古代からの形式そのまま純粋な形で引き継がれてきた……元々神道方支配と仏教方支配とに分けて祭事を行っていたため、明治期の神仏分離政策にも影響されなかったのだそうです。神と仏は別のものであるという最初の前提から離れることなく、それぞれ尊重すべきものとして対応してきたと考えると、単に「変えなかった」のではなく、非常に理知的な判断を以てあえてそのまま維持するという、強い意志の存在をも感じます。
水の神に呼ばれた川上御前がまします山、そこにかかる雲が泰澄大師を引き寄せ、流れる美しい水の音にちなんだ名前を授けられた土地はたくさんの神と紙によって守られることとなった。生命の源である水、その水を豊富に与えてくださる山やま、そこで紙すきを教えてくださった川上御前、神仏と触れ合う場所をととのえてくださった泰澄大師、そして今までその地に住み仕事を続けてきた名もなき先人たち。これらすべてのものへの敬意と感謝の心が、それぞれの身分や地位や立場、時代をも超えて脈々と繋がっている―ーーそれこそが真に「伝統」と呼べるものだとすると、越前和紙の里は古来から自然と「伝統」を体現している稀有な土地といえるでしょう。
参考:「神と紙 その郷」紙祖神岡太神社・大滝神社 重要文化財指定記念誌
続いてきた理由 七 ― 2015/12/15 15:05
あっというまに師走となりました。一年早いですね。
さて、この間久しぶりに両親がこちらに来まして。子供たちが学校に行っている間、母は新宿で同窓会、父と私は兵馬俑を観に上野へ行ってきました。
「特別展 始皇帝と大兵馬俑」東京国立博物館@上野

これがもう、良かった。いやもう↑これ見ただけで面白そうなのはわかりますが、予想を超えた部分で。
メインの展示物はもちろん兵馬俑で、そのリアルな体つき、表情の豊かさは比類ないものでしたが、意外なことに細かいものの展示が素晴らしくよかった。造型や細工が半端無くレベルが高い。日本がまだ縄文土器の時代に、精巧な細工を施した壺や甕、様々な武器や馬具、装飾品、水道管や瓦、漆塗まである。果ては子供のおもちゃらしき陶製の魚。量産していたらしく型まで残ってる!電気もガスもない、金属の道具もふんだんにあったわけではないだろうに、何なんだこの技術力!
学校で習った秦の始皇帝は、中国初の中央集権国家を作り、圧政をしき焚書坑儒という残虐なこともやらかした暴君というイメージだった。だがこの展示物を見て確信した。
始皇帝の時代は、技術を持つ者がその才を存分に活かし、高品質なものを作れるだけの豊かさと余裕があったのだ。
とはいえ、依頼者=権力者の意に沿わぬもの・出来が悪いものを作ったりしたらそれこそ命を取られたり、その職人だけでなく所属する工房、下手すれば村全体の存続も厳しいものになったろう。文字通り命をかけて作っていたのかもしれない。しかし、それでなくとも庶民ならば、今日はよくても明日はどうなるかわからないという時代、一か八かの勝負に賭ける意味は今よりずっと大きかったのではないか。自分の腕一本で、文字通り家族や同胞の命を支える気概は、今と比べ物にならないくらい強かったのではないか。
何より、展示されている品物のひとつひとつが、あまりにも丁寧なつくりで造形的に優れたものばかりで、ただ命令されて作っただけとは思えないのだ。作り手の並々ならぬ情熱
、意気込みがひしひしと感じられる。権力に阿らない・囚われない、自分自身の内側から湧き上がる、自由な意思と行動がそこには見える。
元々は、山あいで農耕や牧畜を営む小勢力にすぎなかった秦は、700年をかけて競合する国との戦いに勝ち抜き、始皇帝を輩出して中国初の統一帝国を築き上げた。始皇帝の死後は奸計にあい滅してしまったが、何年もかけてこの国に集められた技術者たちは、一体どこに散っていったのだろう?
海を越えた辺境の地、まだ新しい国の、そのまた奥「山あいの村」は、かつての秦を思わせただろうか?
父と娘で、夢中になって観ていてあっという間に二時間。さすがに疲れたので、公園内の精養軒にて遅いお昼。正統派洋食といった趣のビーフカレー美味しかった!
いい年してランチもお土産も父に奢って貰ってしまった。しかもこんなの笑
ありがとうございますお父様(≧∇≦)

姿勢がいつもよろしい兵馬俑さま、ダラな私を色々と支えてやってくださいませ。
参考:「始皇帝と大兵馬俑」図録(上野・国立博物館にて販売中)
続いてきた理由 六 ― 2015/10/05 16:48
秋も深まりました。和紙の里の秋祭りはもうすぐです。
日付は、毎年
10/11・12・13
の三日間と決まっていて、今年は日月火。最終日は平日となってしまいました。
画像は重要文化財指定の社殿。(「玄松子の記憶」より)

春の祭りは岡太(おかもと)神社中心の「紙のまつり」ですが、秋は、さらに歴史の古い「大瀧神社」が中心。主祭神である国常立命(くにとこたちのみこと)・伊奘諾尊(いざなぎのみこと)の二柱の神を山上の奥の院から里宮にお迎えします。社伝によれば、大瀧神社は推古天皇の御代(592-638)大伴連大瀧(おおとものむらじおおたき)の勧請により始まり、ついで奈良時代・養老三年(719)、泰澄大師が紙祖岡太神社(川上御前)を御前立、国常立命・伊奘諾尊の二柱の神を主祭神として配し霊場を開き、大滝寺を建立。神仏習合の地となりました。
国常立命は天地開闢の際に出現した神で、国土形成の根源神・国土の守護神とされています。伊奘諾尊は妻のイザナミとともに国産み・神産みの神であり、日本の島々をはじめ、木・海・水・風・山・野・火など森羅万象の神を産みました。
日本の原始信仰は、生活の糧である水とその源流たる山に対する畏敬の念=自然崇拝から生まれ、祖先の霊や氏神といった祖霊信仰とともに、古代の人々の精神の中に生き続けてきました。山におわす水分明神(みくまりみょうじん)がいつしか
「みくまり」(水分…水配り)の神から
「みこもり」(御子守…子育て)の神の信仰へと変化していったことからわかるように、水は何かを産み出す霊力のあるものとされていたようです。
そもそも岡太神社に祀られる祭神の発祥は「水の神」。古くから岡太川(川上御前が川上からいらしたといわれている川)の上流に「地主神」「産土神」として鎮座され、「水波能売尊(みずはめのみこと)」「水分神(みまくりのかみ)」として祀られていたそうです。
まさにその信仰を裏打ちするかのように、山から湧き出す豊かな水によって発祥し発展した紙漉きの業。元々山と水の恵みを敬う神聖な場所であったからこそ、水と関係の深い技術を持つ者たちを引き寄せたのではないでしょうか。「川上御前」がこの地を選ばれたのも、この神々に呼ばれてのことかもしれません。
>>不定期に続く
参考:「神と紙 その郷」紙祖神岡太神社・大瀧神社 重要文化財指定記念誌
続いてきた理由 五 ― 2015/09/04 12:34
晴れ間もつかの間、不安定な空模様の9月ですね。

さて渡来人の数についてですが、公式の記録に残っているのは、当時の王族と親交があり政治力かつ統率力のある指導者の下にまとまった大きな集団の話だけで、具体的な人数の記載などはないようです。なので正確な数は不明ですが、この時代の急激な人口増加から推測すると、一説には100万~150万人もの人数が入ってきていたとも言われています。
折しもシリア難民の問題がニュースで盛んに取り上げられていますが、今よりずっと人口が少なく土地も余っていたであろう時代の日本でも、言葉もろくに通じない、見ず知らずの外国人集団を受け入れるのはやはり大変なことだったでしょう。少数なら同情もし手厚くもてなしたかもしれませんが、現在の移民問題と同様に、伝手をたどり次から次へとその数を増やすうち、記録に残らない程度の小競り合いや揉め事の類はいくつも起きたことでしょう。だからといって帰る場所はもうない。それにせっかく戦乱を逃れてきたのに、ここでまた争い殺しあうのはあまりに愚かだし、双方にとって不幸だ。ではどうする?
お互いに「利」のあるつきあいをしていくしかない。
誰にとっても役に立つ技術をもってさえいれば、出自にかかわらず、どこにいっても生きていける。さらに技術を独り占めするのではなく分け与えるという姿勢であれば、むしろ歓迎され、良い関係を築いていけるし、技術を生業として長く継承していくこともできる。渡来人たちが単なる戦争難民ではなく、職能集団としての性格を濃くしていったのは、必然の流れだったのでしょう。国籍も、地位も身分も性別も関係なく、力で抑えこむのでもない、役に立つ技術によりあらゆる土地・あらゆる階級の人々と交流し、思うままに融合したり離れたり、という生き方は、ある意味究極の自由人ともいえるかもしれない。最初の頃一族で固まって暮らしていた渡来人たちが次第に各地へと広がり散らばって、国と人とに溶け込み、ともに現在の日本国と日本人を形作って来られたのも、ひとえにこの、枠にはまらない「職人気質」な生き方を選択したおかげなのでしょう。
その「職能」のひとつであった製紙業。越前和紙の発祥は伝説によると、
「川上からやってきた、綺麗な着物を着た女性」
から製紙法を習ったのが始まりだとされています。
女性の正体は不明で、継体天皇のおつきの女性であるとか、諸説ありますが、明らかに土地の人間ではない、どうみても富裕層といった外見の女性が突然現れて手ずから技を教え、またいなくなったという話は、まさに当時の職能で生きる人間の動きそのもの。性別関係なく、自由にあちこち移動しつつ、ここと決めた土地に技術を根付かせ継承させていくという生き方にぴったり合致しています。
川上御前を紙祖神にいただく越前和紙の里では、紙を漉く主力は女性です。紙漉きに必要な綺麗な水が豊富にある、という好条件がある土地に根ざした産業ではありますが、昔から決して閉鎖的ではなく、常に新しいものへの好奇心を失わず、来るものは拒まず、必要とあらばどんどん外に出ていく、という開かれた場所でもあります。
それにしても、川上御前なる女性は、なぜこの土地を選んでくださったのでしょう。綺麗な水が豊富にある、ということは大きな理由だったのでしょうが、見つけるきっかけはなんだったのか。元々そういう土地を日本各地に探しまわっていたのか、それとも誰か紹介者のようなものがいたのか。いずれにせよ、川上御前がたまたま?この土地を選ばなければ、今そこに集落は存在しなかったかもしれない。今これを書いている私もいなかったかも。あえてそれを運命とは呼びません。つくづくと、先人の「判断」と「選択」に感謝です。
>>以降、不定期に続く

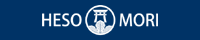

最近のコメント