続いてきた理由 四 ― 2015/08/20 17:15
しばらく暑さで溶けていました。気づけば盆明けで雨も降ってすっかり涼しく(^_^;)休みボケで頭が働きませんが(それはいつもか)がんばって更新。
こちらは帰省時に初めて入った「記憶の家」。思った以上にすっきりした居心地の良い空間でした。千客万来♪

さて、秦氏。
ネット検索を駆使し調べた結果をまとめると、秦一族のルーツはこんな感じ。
応神天皇16年(西暦285年?年代は不明確)弓月君(ゆづきのきみ)が120の県(こおり)の人民を従え日本に移住し帰化、山背国(京都南部)を拠点とし日本全国に分布する。朝廷の蔵など財政面を司る一方、新羅系の技術者を擁して各種技術部門の主導権を握り、鉱山開発や土木事業など殖産氏族としての活動が顕著であった。
ちなみに「秦」という名前には、
◯秦の始皇帝の末裔が中国から半島南部に逃れ、一族で「秦」を名告っていたという説
◯弓月君の連れてきた民は養蚕や職絹に従事しており、その絹織物が柔らかく「肌」のようにあたたかいことから「波多」の名を賜ったという説
◯朝鮮語で「海」を意味する「パダ」に由来するという説
等など諸説あるが、このように大陸や朝鮮半島からたくさんの人々と技術が日本に渡来したことで、大和朝廷が大いに栄えたことは確からしい。
この弓月君、本当に秦の始皇帝の末裔であったかどうかはわからないが、「120の県の人民」を連れて…とはなかなか凄い。始皇帝が作った郡県制は、郡・県・郷・里の順に分かれている。上から2番目の単位である「県」、どのくらいの人数になるのかはよくわからないが、一県あたり100人としても1万2千人!これだけの人民をまとめ上げ新天地へと導いたその求心力、半端ではない。そしてそういった人物に「奏上」された応神天皇の器の大きさ。移住の希望を受け入れ人を派遣するも、新羅の妨害でなかなか叶わず三年が経つとみるや、新羅国境にさらなる精鋭を差し向け、約束通り無事弓月君一行を渡来させた。聖徳太子よりさらに数百年もさかのぼり、まだ日本という名前もついていない海を隔てた辺境の地が、長く続く戦乱に蹂躙されつづけてきた人々にとって、一か八かに賭ける価値のある希望の国だったのかと思うとゾクゾクする。
平均寿命が今の半分以下だった時代、戦乱を、危険な船旅を生き延び、知らない土地・知らない人々の間で働き生きていくというのがどれほどすごいことか、想像を超えている。ほとんど奇跡に近いほどの運の強さ、超人的な体力気力・バイタリティのある人間ばかりの集団、しかもただの難民ではない技術者集団を受け入れることは、日本国にとっても十二分にメリットがあった。天皇のもとにまとまった平和な国に、一族は馴染み溶け込んで全国へと散っていった。彼らの持つ技術には、政治的立場や思想は関係ない。技術に対する敬意と、必要な対価を支払う能力がある人間に請われれば、どこでも自由に行っただろう。気に入った土地には長く住みついて、地元の人間と結婚し、跡継ぎを育てたりもしただろう。そういう動きの中のひとつにきっと、紙の製法もあったにちがいない。
>>続く
【参考】
世界大百科事典 第二版「秦氏」の解説
日本大百科全書(ニッポニカ)「秦氏」の解説
wikipedia 秦氏、応神天皇、弓月君
続いてきた理由 三 ― 2015/07/19 15:02

関東ついに梅雨明け!暑いです!(記事と画像はあんまりというか全然関係なし^^;)
さてここでまたまた聖徳太子に話を戻し、関連する年表をおさらいしてみる。
574年 誕生(厩戸皇子となのる)
593年 皇太子となり摂政の任に就く(数え年20歳)
594年 仏教興隆の詔を発する
603年 冠位十二階を制定(30歳)
604年 十七条の憲法制定
607年 遣隋使派遣
610年 中国より曇徴来朝、紙の製法を伝える
611-615年 「三経義疏」を著す
615年 「法華義疏」を著す
622年 死去(享年49歳)
この歳になってあらためてこの年表をみてみると、
20歳で(!)摂政という国の政治を動かす地位につき、
30歳から破竹の勢いで新制度を打ちたて運用し、
当時の最高技術を外国から取り入れ国内外から職人も集め、
寺社建築・製紙普及という一大公共事業を各地で多数執り行う中
自分自身でもいろいろ造ったり書いたりして、
さらに外交でも大国に対し一歩も引かず独立国家として自国をアピール
…って、どんだけ超人なのか…
当時の実力者・蘇我馬子がバックにいるとはいえ、摂政になった翌年いきなり仏教やります宣言をしているあたり、よほど若い頃からいろいろと国のために何をなすべきか考えながら、勉強したりしかるべき人と繋がりをつけたりして準備していたんだろう。当時の仏教は学問であり、最高の知性がそこに結集していたから、仏教を広めることすなわち日本人の知力UPに繋がるとの思惑もあったと思う。それだけではなく、製紙という産業の世界的な将来性に気づき、いち早く国内生産の道をつける当たり、おそるべき慧眼だ。そして遣隋使を送った年の三年後には曇徴を招聘しておそらく最新の紙の製法を学び、翌年から仏教についての書を作り始める(=書きつけるための紙も当然用意したろう)というとてつもないスピード感。
聖徳太子については様々な伝説が残っており、十人の話をいっぺんに聞いていっぺんに答えたとか。それくらい聞き上手だったということなのだろう。人は誰しも自分の話を聞いてほしいもの。最初から最後まで真摯に耳を傾けてくれて、的確なアドバイスなり回答なりを与えてくれるような上司を慕わない部下はいない。太子は、当時日本で普通に採れた楮を使って今日の和紙の原型となる紙をつくりだしたと言われているが、なるほどこういう人ならばやりかねない、というかきっとやったに違いない。骨身を惜しまず協力する人間も数多くいただろうと思う。紙というものは飛鳥時代よりもっと昔からあったけれど、製紙業を日本の一大産業として育て広めたのは、確実に太子の類まれな才能・人徳による偉大な功績といって過言ではない。
そんな超人・太子の側近として歴史に名を残している
秦河勝(はたの かわかつ)。
渡来人集団のひとつ、紙と関係の深い秦氏について次は考えてみます。
>>続く
続いてきた理由 二 ― 2015/07/06 14:36
日本に製紙を広めるきっかけを作ったのは聖徳太子!
というのが前回のお話でした。今日はそこから少々時代を遡ってみます(授業っぽい(^^))。そもそも、紙という技術が生まれたのはなぜか?どこから?
紙以前に、「ペーパー」の語源にもなった古代エジプトのパピルス、メソポタミアの粘土板、古代中国の甲骨、東南アジアの木の葉や樹皮などなど、古くから世界各地で何らかの「記録」が行われていたことは確かです。衣食住を満たすこともままならなかった時代なのに、いや多分そういう時代だからこそ?個々がもつ知識や情報を形に残し子孫に伝えることで、自らの属する集団を長く存続させていこうとしたのではないか?共同体のスケールが大きくなり、ひとつの国としてまとまってくればなおさらその必要性は高まったことでしょう。「紙」が記録のための媒体として選ばれ、ブラッシュアップされつつ凄い勢いで世界各地に広がっていったのは、必然の流れだったのかもしれません。
ちなみに、長く「紙の発明者」とされていた蔡倫は実は「偉大な製紙技術の改良者」であった、というのが今では定説となっています。蔡倫は後漢時代の人で、西暦105年に紙をつくり皇帝に奉ったところ、帝はその才をいたく褒められ、これよりこの紙を用いないことはなかった…と「後漢書」に記載されています。(←漢文っぽい表現ですねー。つまりもうこれからはこれしか使わない!というくらい出来が良かったということです(^^))
「紙」という漢字は、蔡倫以前から存在していました。
糸:蚕糸を撚り合わせた形により糸を示す象形文字
氏:匙の形を示す象形文字、滑らかなことを表す
すなわち糸+氏で
「蚕糸を匙のように滑らかに薄く平らに漉いた、柔らかいもの」
をいいます。つまり中国において、元々の紙の原料は「絹」だったのですね!
ただし絹を原料とした紙はもろく、保存性も悪くさらに高価でもあったので、安価で丈夫な麻などの植物性原料にとってかわられたようです。蔡倫より前、前漢時代の遺跡から出土した紙の原料はすべて麻類の繊維でした。
蔡倫は発明者ではないものの、紙という製品を製法から見直し、コスト的にも品質的にも大幅に改良・実用化しました。情報が書き込める書写材料としての紙の完成により、用途も広がり需要も増え、業としての製紙法も確立、豊富な生産を可能としました。その結果紙は中国のみならず全世界に広がり、印刷技術の発展のきっかけにもなりました。
さすがは「歴史を創った100人」中七位にランクインした蔡倫さんです。
さて話を日本に戻します。聖徳太子の時代、既に紙は日本にありました。1世紀頃から大陸との国交により人や物の往来があったことで、日本人はかなり昔から紙というものを知っていたようです。現に、285年「論語」「千字文」などの書物が中国から日本に送られてきた、と日本書紀に記されています。
ただ蔡倫の紙「蔡侯紙」は麻や漁網といったいわゆる(ボロ布)で作られていて、仕上がりがあまりキレイではなかったのと扱いが難しかったのとで、日本では以前から織物に使われていた楮などの靭皮繊維を原料とした紙が好まれたようです。
!!!楮!!!
>>続く
参考資料:「越前和紙の里」岡本小学校
「紙の歴史と製紙産業の歩み」財団法人 紙の博物館
ホームページ「紙への道」←かなり秀逸なサイトです、必見。
続いてきた理由 一 ― 2015/07/03 15:31
夏至も過ぎ、そろそろ梅雨明けの兆しが見えてきても良さそうなものですが、まだまだといった感じですね。関東は未だ荒天のところも多く心配ですが、皆さまどうぞご自愛を。
雨の日に家にいることが嫌いではない、基本引きこもり体質の私。今しばらく、和紙の歴史を勉強しようかと(し直そうと)もくろんでおります。
さてこの季節といえば期末テスト。ちょっと前まで百人一首の上の句下の句やら方程式やら飛鳥時代がどーしたこーしたとやらで喧しい我が家でした。しかし何で兄や姉は妹の勉強となると口を出したがり語りたがるのか。黙って自分の勉強をせんか。まあそれはともかく・・・今回のキーワードはズバリ、聖徳太子。
どんな教科書にも必ず太字で書いてある出題必須の超定番・聖徳太子の3大功績
十七条の憲法
冠位十二階制
遣隋使派遣
冠位十二階制
遣隋使派遣
これが実は、日本の製紙業の広まりに相当大きな関係がある!
何故か?律令制以降、公的文書の増加・仏教伝来等で紙の需要が飛躍的に増えたから。
より質の良い紙をより多く生産するために、全国的に製紙を奨励したと言われています。このため太子を紙祖として祀っている産地もあるとのこと。太子みずから紙を漉いたという説もあります。
当時の大国にならいつつも阿ることなく、法を基にした独立国家としての日本の礎を作ったスーパー国際人である聖徳太子により、製紙が国家事業として確立されていったと思うと、胸熱ですね。
この後さらなる太字案件
701年 大宝律令制定
にて
図書寮と紙戸で製紙を行うこと
紙を調(税の一部)として納めること
紙を調(税の一部)として納めること
も決まり、業としての製紙は以降まさにビッグウェーブに乗っていきます。
>>続く
参考資料:「紙の歴史と製紙産業のあゆみ」財団法人 紙の博物館

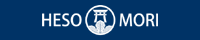

最近のコメント